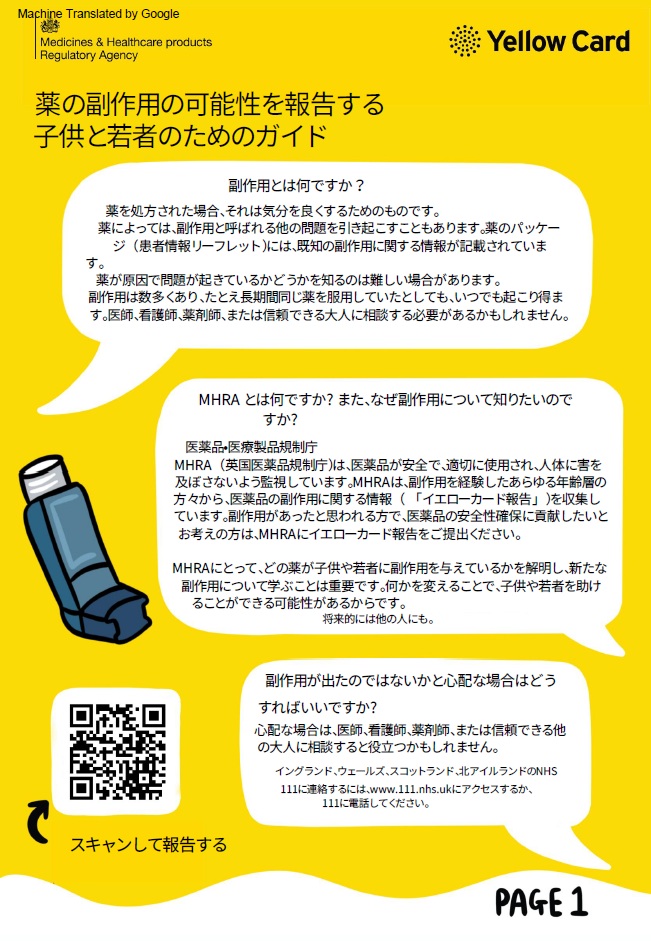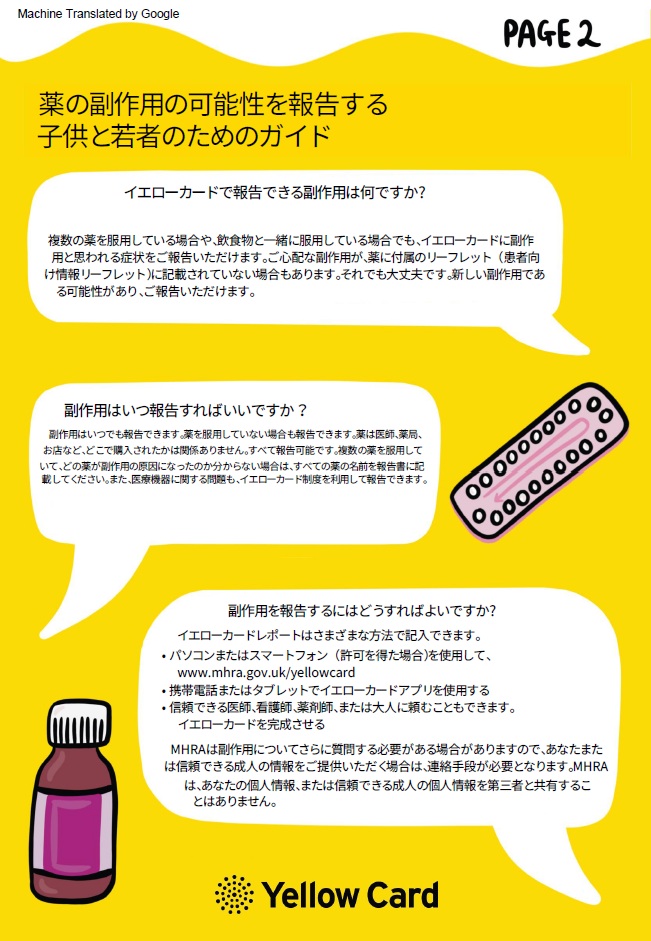World Patient Safety Day (世界患者安全の日)の9月17日、英MHRAは17日、英教育省と協力して Yellow Card scheme を通じた医薬品の副作用報告制度について生徒たちが学ぶよう、学校向けの法定ガイダンスに組み込むと発表しています。
【MHRA 2025.09.17】
MHRA and Department for Education embed medicine safety into school curriculum to empower young people
https://www.gov.uk/government/news/mhra-and-department-for-education-embed-medicine-safety-into-school-curriculum-to-empower-young-people
MHRAでは子どもや若者向けのチラシ(ガイド)を作成、副作用の可能性を報告することがなぜ重要なのかを、他の子どもや若者に理解してもらうのに役立つとしています
Reporting a possible side effect to a medicine – a guide for Children and Young People(Google翻訳)
https://yellowcard.mhra.gov.uk/children-and-young-people-guide
このガイドの開発にあたっては、2022年11月から約半年をかけてユーザーデストが実施されていて、論文も発表されています
Assessing and further developing age-appropriate information for young people about reporting suspected adverse drug reactions
(Br J Clin Pharmacol. 2024 Mar;90(3):863-870.)https://bpspubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/bcp.15971
ユーザーテストは13~18歳の21校の生徒を対象に実施
研究結果によれば、参加者の27.9%の生徒が現在何らかの薬を服用していて、38.1%がこれまでに副作用の経験があると答えています。(ちょっとビックリ)
質問の項目と自由記載での具体的な副作用経験(エクセルファイル)
https://bpspubs.onlinelibrary.wiley.com/action/downloadSupplement?doi=10.1111%2Fbcp.15971&file=bcp15971-sup-0001-+Supplementary+Data.docx
上記によれば、多く寄せられた副作用経験は次の通りだったそうです
- 経口避妊薬38
- ペニシリン30
- covid-19ワクチン27
- アセトアミノフェン16
- ADHD治療薬15
- 抗ヒスタミン薬14
- セルトラリン12
- フルオキセチン12
- ロアキュタン/イソトレチノイン11
- イブプロフェン10
そして生徒たちに、上記のガイドについて理解度を尋ねたところ、92.8%が理解できたと答え、また、90.8%がガイドを読んだ後にADR(adverse drug reaction)をよく理解できたと答えています。
また、ADRを報告することに「不安」を感じる若者の割合は、このガイドを読む前は13.3%であったのに対し、読んだ後は4.1%に減少。さらに、84.5%の若者が将来副作用(side effect)について報告する意思があると回答しています。
またこの研究では、ごくわずかですがYellow Card scheme で実際に報告したことがあると回答しています。
研究者らは、調査対象が私立学校の割合が多いなどの偏りがあるとしながらも、子どもや若者を支援するための関連授業の実施を行うことで、イエローカード制度への潜在的な報告者層が大幅に拡大し、若者が成人期へ移行する過程で医薬品に関する知識とスキルを向上させ、最終的には彼らの将来的な報告が医療製品の安全な使用と患者安全の向上に役立つものとなると結論付け、今回の法定ガイダンスへの組み込みに至ったと思われます。
日本でも、英国のような患者が薬の副作用についての直接報告する仕組みは2012年からスタートしています。(→TOPICS 2012.03.26)
患者の皆様からの医薬品副作用報告(PMDA)https://www.pmda.go.jp/safety/reports/patients/0024.html
システム操作マニュアル(PMDA)
https://www.pmda.go.jp/files/000274238.pdf
しかし、医薬品等安全対策部会(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi-yakuji_39211.html)での報告によれば、2024年度に寄せられたのは210件に留まっており、広報や周知についてはまだまだ改善の余地ありそうです。
そういった意味で、今回の若者に向けた周知の取組は日本でも参考にすべきであり、「くすりとどう関わるか」ということを一人一人に育み、しいては日本のお任せ医療といった医療文化を変えていく手段となるのではないのでしょうか。
参考:
Medicine safety embedded in school curriculum ‘to empower young people’
(The Pharmacist 2025.09.17)
https://www.thepharmacist.co.uk/news/latest-news/medicine-safety-embedded-in-school-curriculum-to-empower-young-people/
関連情報:TOPICS(リンク切れあり)
2012.03.26 オンラインによる患者副作用報告の試行事業が開始
2009.01.10 患者副作用直接報告は、医療専門職からの報告を補完する
2008.02.19 イエローカードオンライン副作用報告システムが本稼動(英国)
2025年09月20日 11:42 投稿